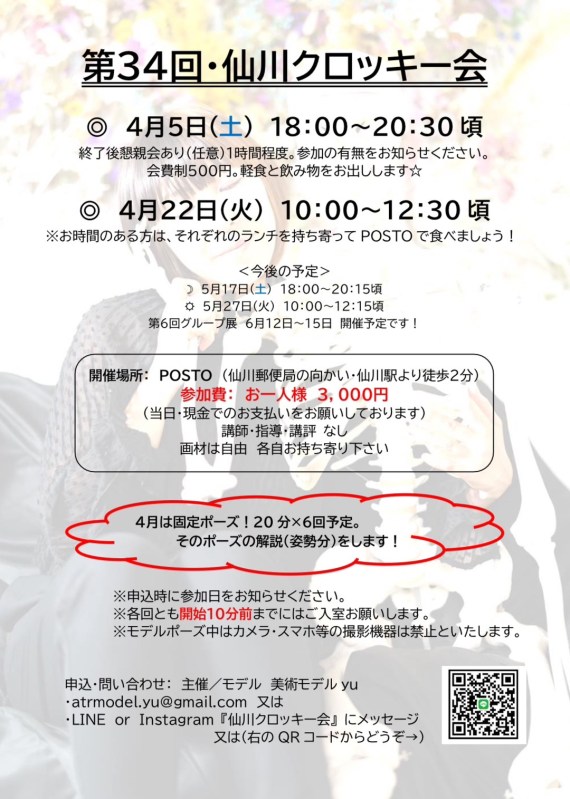現代フランスの哲学者の中で、このような問いに答え得るのは、ミシェル・フーコー、ジャン=リュック・ナンシー、アラン・バディウ、ポール・プレシアードといった思想家たちが考えられます。それぞれの視点から、この問題を分析してみましょう。

1. ミシェル・フーコー(Michel Foucault, 1926-1984)
フーコーの『性の歴史』は、人間の性的志向や趣向がどのように歴史的・社会的に形成されてきたのかを分析しています。彼によれば、性的指向や趣向は「内的な本質」ではなく、「言説」として構築されてきたものです。
- 19世紀以前は、性的行動が「罪」や「逸脱」として捉えられていたが、19世紀以降、医学や心理学が発展する中で、人々は自分の性的指向を「アイデンティティ」として意識するようになった。
- 近代社会は「規範的な性」を管理する一方で、逸脱した性的嗜好(サディズム、マゾヒズム、フェティシズムなど)を「異常」として分類し、医学的・法的な枠組みでコントロールしようとしてきた。
- しかし、こうした分類は「真実」を明らかにするのではなく、むしろ新たな「欲望の形式」を生み出す結果となった。つまり、「人間の性」は、社会がどのように語り、管理しようとするかによって、無限に多様な形態を取る。
フーコーの視点に立つと、人の性的嗜好がバラエティーに富んでいるのは、もともと「人間の欲望に多様性がある」というよりも、「社会がどのように性を定義し、分類し、管理してきたか」によるところが大きいといえます。そして、新たな言説やメディア環境が、これまで想像されなかったような性的趣味を生み出しているのです。
2. ジャン=リュック・ナンシー(Jean-Luc Nancy, 1940-2021)
ナンシーは、性を「個の孤立」ではなく「関係性」の問題として捉えます。彼の『性の意味』(La signification du sexe) では、性は「他者との接触」と「自己の限界」の問題であると論じています。
- 人間の性は単なる生理的な欲望ではなく、他者との関係性の中で意味を持つ。
- 性的志向や趣向の多様性は、単に「個人の内的な選好」ではなく、文化や社会の中で「意味」を与えられることによって形成される。
- ナンシーによれば、「想像だにし得なかった性的趣味」は、すでに存在している価値観や意味体系の枠外で「新たな接触の可能性」が開かれることによって生じる。
つまり、性は「個人の好み」というより、「関係の可能性」そのものの多様性が生み出すものと考えられます。そして、新しいメディアやテクノロジーが、新たな関係の可能性を開き続ける限り、想像もつかないような性的趣味は無限に現れ続けるでしょう。
3. アラン・バディウ(Alain Badiou, 1937-)
バディウは、愛や欲望を「真理の探求」として捉えます。『愛の多様性』では、性的志向や趣向が「単なる選好の問題」ではなく、「人間存在の根源的な問い」と結びついていると述べています。
- バディウによれば、愛や性は「アイデンティティの一部」ではなく、「偶然の出来事」として立ち現れる。人は、社会的な枠組みの中で欲望を持つのではなく、予期せぬ出会いによって新しい欲望を発見する。
- 性的嗜好の多様性は、愛や欲望が「個別的な偶然性」によって動かされているために生じる。
- 想像だにし得なかった性的趣味が存在するのは、人間の欲望が決して固定されたものではなく、「歴史的な出来事」として常に変容し続けるからである。
バディウの考えを踏まえると、性的指向や趣向の多様性は、単なる社会の産物ではなく、人間が「新しい愛や欲望の形」を発見し続けるプロセスの中で生まれてくるものと考えられます。
4. ポール・プレシアード(Paul B. Preciado, 1970-)
プレシアードは、ジェンダーやセクシュアリティを「生物学的なもの」ではなく、「バイオ・ポリティクス(生政治)」の問題として分析します。彼の『テストステロン日記』(Testo Junkie) では、性的志向や趣向がいかに「テクノロジーや薬理学と結びついているか」を論じています。
- 性的指向や嗜好は、生物学的に決定されるのではなく、化学的・医療的な技術、ポルノグラフィー、デジタルメディアなどの影響を受けながら変容する。
- 「性的趣味の多様性」は、メディアや社会制度が「欲望の形」をどのように構築するかによって変わる。
- 21世紀に入ると、バイオテクノロジーの発展によって、従来のジェンダーやセクシュアリティの枠を超えた「新たな身体の在り方」が可能になり、これまで考えられなかった性的嗜好や実践が生まれるようになった。
プレシアードの視点に立つと、性的指向や趣向の多様性は、単なる個人の選好ではなく、テクノロジーと政治的な力がどのように作用するかによって変化するものであると考えられます。

現代フランスの哲学者たちは、人の性的志向や趣向の多様性を、単なる「生まれつきの傾向」ではなく、「社会的・歴史的・技術的な影響のもとで変化するもの」として捉えています。
- フーコーは「言説と権力の構築物」として分析し、
- ナンシーは「関係性の可能性」として考え、
- バディウは「愛や欲望の偶然性」として捉え、
- プレシアードは「バイオ・ポリティクスとテクノロジーの影響」として論じました。
したがって、「なぜ性的嗜好は多様なのか?」という問いへのフランス哲学の答えは、「それは本質的なものではなく、社会や文化、歴史、テクノロジーの変化とともに絶えず変化するものだから」というものになるでしょう。そして、想像もし得なかったような性的趣味が存在するのは、人間の欲望が決して固定されたものではなく、歴史やテクノロジーの中で無限に変容していくからなのです。
フォトエッセイ 「恥ずかしいです・・姿を見られるのが怖いです」